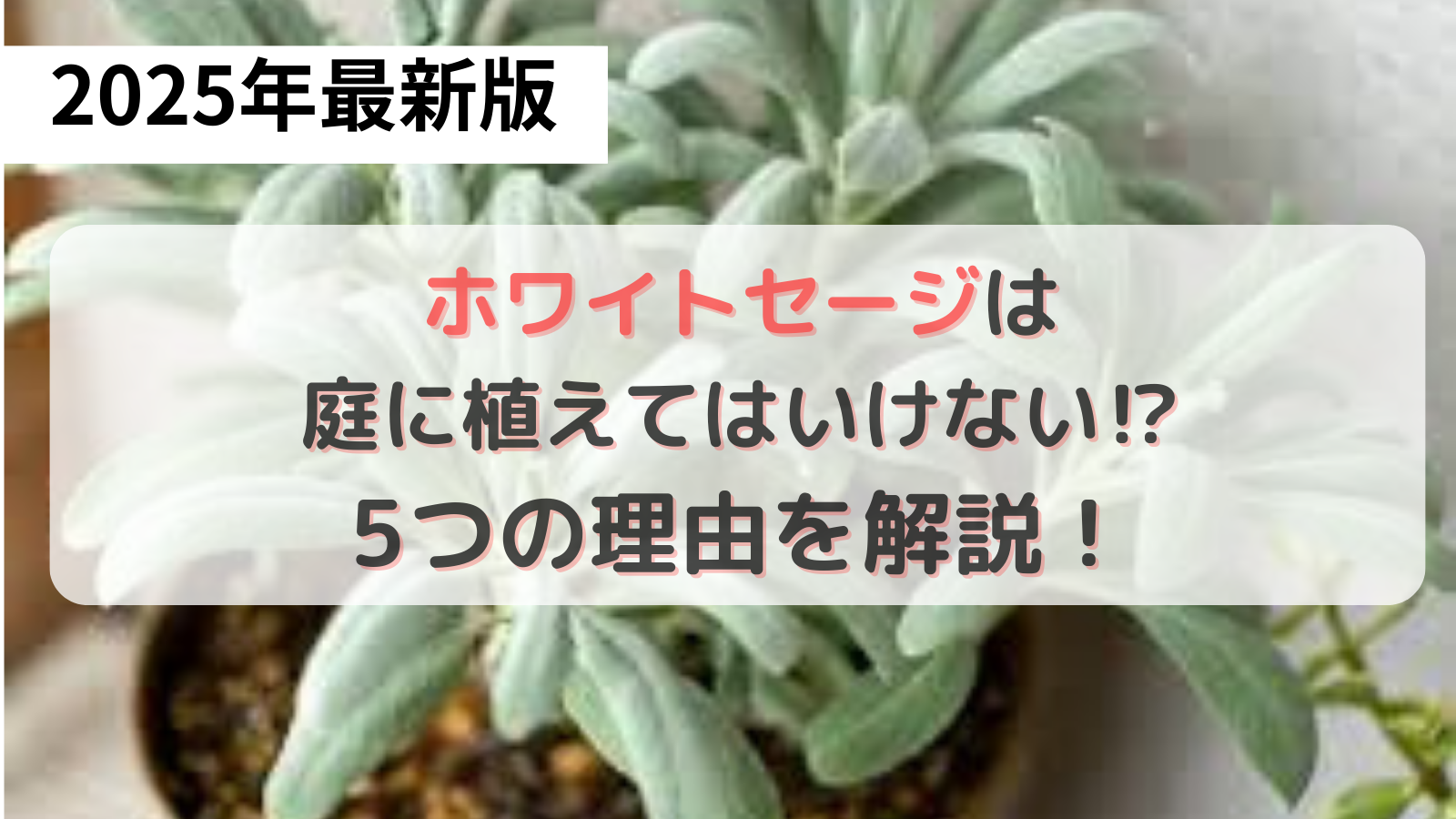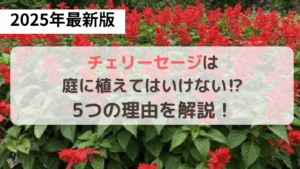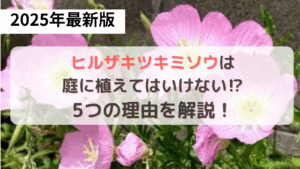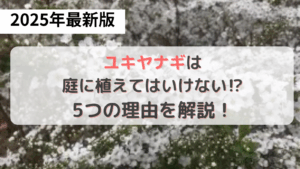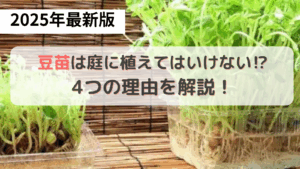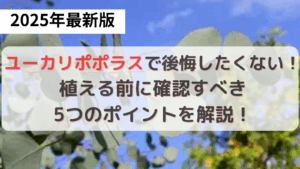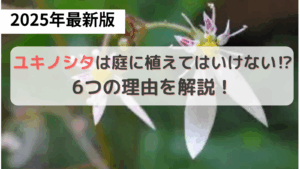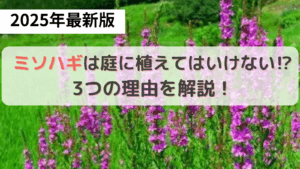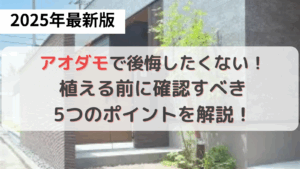ホワイトセージは庭に植えてはいけないって聞いたんですけど、どうしてですか?



理由が5つありますが詳しく解説しますね。
庭づくりを考えるとき、香りや見た目の美しさから「ホワイトセージを植えてみたい」と思う人は少なくありません。
スピリチュアルな浄化効果やおしゃれな雰囲気で人気がある一方で、実際に庭に植えた人からは「すぐ枯れてしまった」「倒れやすくて手入れが大変だった」という後悔の声も多く聞かれます。
本記事では、なぜホワイトセージを庭に植えると後悔しやすいのか、実際の体験談や注意点、代わりにおすすめの庭木や正しい楽しみ方について詳しく解説します。
最後には失敗しない庭づくりのポイントも紹介していますので、これから庭木を選ぶ方はぜひ参考にしてください。
- ホワイトセージの基本的な特徴
- 庭に植えると後悔しやすい理由
- 実際の失敗談
- 代わりにおすすめの庭木
- もし植えてしまった場合の管理方法



庭づくりは意外と難しいもの。植える木の選定を間違ったり、全体のバランスが悪く後悔してしまうこともありがちです。
👉 外構工事一括見積サービスを利用すれば、複数の業者を比較して、自分に合った庭づくりのプランを見つけることができます。
庭木の選び方や手入れは思ったより大変なものです。自分だけで判断すると「思った以上に剪定が大変…」「もっと他に合う庭木があったかも」と後悔してしまうことも。
無料の一括見積サイトを使えば、複数の外構業者から提案を受けられるので、「費用感」や「手入れのしやすさ」を比較でき、納得して決められるでしょう。


「タウンライフ外構工事」を利用すると、無料で複数の業者の見積もりが届きます。
しつこい営業もありませんから安心して利用できます。
庭づくりに悩んでいる方はぜひ利用しましょう。
\ 全て無料 で安心!/
ホワイトセージとはどんな植物


ホワイトセージ(White Sage、学名:Salvia apiana)は、北アメリカ西部、特にカリフォルニア周辺の乾燥地帯を原産とするシソ科の多年草です。
古くからネイティブアメリカンに「聖なるハーブ」として重用され、葉を乾燥させて焚くことで空間を清める浄化作用があると信じられてきました。
近年ではスピリチュアル系のアイテムやハーブとして注目され、日本でも観賞用やアロマ的用途として育てられるケースが増えています。
しかし、日本の庭に直植えすると環境が合わず、後悔してしまうケースが多いのも事実です。
基本情報と原産地
- 科属:シソ科アキギリ属
- 原産地:北米・カリフォルニア州の乾燥地帯
- 性質:多年草・常緑性
- 耐性:乾燥や日光には強いが、湿気に非常に弱い
ホワイトセージは砂漠のような乾燥した地域で育つため、日本のような高温多湿の夏や雨が多い梅雨には極端に弱いという欠点があります。
見た目や人気の理由
ホワイトセージの魅力は、銀白色の美しい葉と、すっきりとした香りです。
庭に植えるとその独特な色合いが引き立ち、ほかのグリーンとコントラストを生み出します。
また、ドライにしてスティック状に束ね、スマッジング(焚いて煙で浄化する儀式)に使えることから「育ててみたい」と思う人が増えています。
庭木として選ばれる背景
スピリチュアルや浄化のイメージが広まったことで、園芸店や通販でも「ホワイトセージの苗」が手軽に購入できるようになりました。
特にヒーリングやヨガなどに関心のある層から人気があります。
しかし実際には、日本の庭に地植えすると「湿気で根腐れして枯れた」「梅雨を越せなかった」といった失敗が非常に多く、鉢植えで育てるのが現実的な植物といえるでしょう。
ホワイトセージを庭に植えてはいけない理由


ホワイトセージは美しい葉と独特の香りで人気がありますが、日本の庭に直植えしてしまうと多くのトラブルを招きやすい植物です。
実際に「失敗した」「育たなかった」という声は非常に多く、特に以下のような理由が挙げられます。
成長が早すぎて管理が大変
ホワイトセージは乾燥地帯では旺盛に育つ植物で、条件が合えば日本でも短期間で大きく成長します。
苗木のうちは小さく見えても、地植えすると想像以上に広がり、庭の他の植物を圧迫するケースがあります。
定期的に剪定をしなければ樹形が乱れ、見た目も悪くなってしまいます。
根が浅く、湿気で根腐れしやすい
ホワイトセージの根は浅く広がるタイプで、乾燥地帯ではこれがメリットになりますが、日本の梅雨や長雨の環境では逆効果になります。
雨が続くと地中に水分が溜まりやすく、根腐れや病気を起こしやすくなるのです。
特に排水性の悪い土壌では「1シーズンで枯れてしまった」という例が多く見られます。
幹や枝が細く、支えが必要
ホワイトセージは木のように見えても実際はハーブに近い性質を持ち、幹や枝は意外と細く柔らかいのが特徴です。
そのため、成長すると上に伸びて重心が不安定になり、風で倒れやすくなります。庭に直植えした場合、支柱を立てたり、こまめに剪定して高さを抑えたりといった管理が欠かせません。
日本の気候に合わず病害虫が出やすい
原産地のカリフォルニアは乾燥した気候で、病害虫の発生が少ない環境です。
しかし日本では高温多湿によりカビや害虫が発生しやすく、葉に黒い斑点が出たり、根が弱って枯れてしまうことがあります。
特に梅雨から夏にかけては管理が難しく、「庭植えではほぼ越冬できなかった」という声もあります。
他の植物と共存しにくい
ホワイトセージの葉や根には揮発性の成分が含まれ、周囲の植物の成長を妨げる作用(アレロパシー効果)があるといわれています。
そのため、近くに植えた草花が思うように育たず、庭全体のバランスが崩れてしまうこともあります。
ホワイトセージを庭に植えて後悔した人の声・失敗談


ホワイトセージはスピリチュアルな意味合いや浄化効果で人気が高まっていますが、実際に庭に植えてみた人からは「思っていたより難しかった」「結局枯れてしまった」といった声が多く聞かれます。
ここでは、代表的な失敗談を整理します。
想像以上に枯れやすかった
「丈夫そうだから大丈夫だろう」と思って庭に直植えしたところ、梅雨の時期に一気に弱って枯れてしまったという声が非常に多くあります。
ホワイトセージは湿気に極端に弱いため、排水性の悪い庭土では夏を越すのが難しいのです。
大きくなりすぎて手に負えなくなった
小さなポット苗から始めても、条件が合うと急激に成長し、気が付けば庭の一角を占領してしまったケースもあります。
「最初は可愛いと思ったけど、成長スピードに驚いた」「剪定が追いつかず、見た目が乱れてしまった」という後悔の声も少なくありません。
幹や枝が折れやすく、支えが必要になった
見た目は樹木のように見えますが、実際はハーブに近い性質を持っているため、幹や枝は細く柔らかいです。
風の強い日や大雨のあとに「倒れてしまった」「枝が折れて台無しになった」という失敗談もあります。
他の植物と相性が悪かった
「隣に植えていた花が育たなくなった」という声もあります。
ホワイトセージは葉や根から揮発性の成分を出すため、周囲の植物の生育に影響を与えてしまうのです。
その結果、庭全体の調和が崩れてしまい、「植える場所をもっと考えればよかった」と後悔する人も多いです。
管理に疲れて結局は伐採した
「浄化用に育てたい」と思って植えても、実際には剪定・病害虫対策・支柱立てなど、日常的な管理の手間が想像以上にかかります。
そのため「結局は管理しきれず伐採した」というケースも珍しくありません。
植える前に「庭に本当に適しているか」を見極めることが大切です。
ホワイトセージを楽しむ正しい方法


「庭に直植えすると失敗する」といわれるホワイトセージですが、それはあくまで日本の環境に合わないだけの話。
適切な方法を選べば、香りや浄化アイテムとして十分楽しむことができます。ここではホワイトセージを安全かつ長く楽しむための方法を紹介します。
鉢植えで育てるのが基本
ホワイトセージは湿気に弱いため、庭に地植えするのではなく鉢植えで管理するのが最も安全です。
鉢植えなら排水性の良い土を使えますし、梅雨時や冬など苦手な季節には室内や屋根の下に移動することができます。
特にテラコッタ鉢や素焼き鉢は通気性が良く、根腐れ防止に効果的です。
日当たりと風通しを意識する
ホワイトセージは太陽の光を好みます。ベランダや庭先でも、日当たりが良く風通しのよい場所に置くことで健康的に育ちます。
逆に、湿気のこもる場所や日陰ではすぐに弱ってしまうため注意が必要です。
水やりは控えめに
水を与えすぎると根腐れを起こしやすいのがホワイトセージの特徴です。
基本的には土がしっかり乾いてから与える「乾燥気味管理」が基本。
特に梅雨や冬は水やりの頻度を減らし、できる限り乾燥気味に育てるのがコツです。
室内でアロマ・浄化に活用する
ホワイトセージは「スマッジング」と呼ばれる浄化アイテムとして人気があります。
乾燥させた葉を焚けば、お香のように香りが広がり、空間をリフレッシュできます。
庭植えではなくベランダや室内で育てて活用することで、目的に沿った楽しみ方ができるのです。
ドライハーブにして長期保存
収穫した葉は乾燥させて保存すれば、長期間利用できます。
花瓶に飾ったり、ポプリやハーブティーに使ったりと用途も多彩。小さな鉢で数株育てるだけでも、自家製のホワイトセージを十分に楽しめます。
ホワイトセージの注意点とデメリット
ホワイトセージはスピリチュアルな効果や美しい姿で人気がありますが、庭に直植えするとなかなか思うように育ちません。
特に日本の環境では「後悔した」と感じる人が多いため、事前に注意点をしっかり理解しておくことが大切です。
鉢植えで育てるのが基本
ホワイトセージは地植えにすると湿気で根腐れしやすく、越冬も難しいケースがほとんどです。
そのため、日本では庭に直植えせず、鉢植えで管理するのが基本と考えたほうが安心です。
鉢植えであれば場所を移動でき、雨が続く時期や冬の寒さから守ることができます。
庭木としてのスペースが必要
もしどうしても庭に植えたい場合は、十分なスペースと排水性の良い土壌が必要です。
株が広がりやすいため、周囲の植物と干渉しやすく、狭い庭ではバランスを崩してしまうこともあります。スペースに余裕がない庭での直植えは避けたほうがよいでしょう。
他の植物との相性が悪い場合がある
ホワイトセージはアレロパシー(他の植物の成長を抑える作用)を持つとされており、周囲に植えた草花の育ちが悪くなることがあります。
庭全体を花や緑で彩りたい場合、ホワイトセージを地植えすると他の植物の調和を乱す原因になりかねません。
病害虫や環境への弱さ
乾燥地帯が原産のため、日本特有の梅雨や高湿度の夏は大きな弱点になります。
うまく管理できなければカビや根腐れが発生し、あっという間に枯れてしまうことも少なくありません。
さらに、弱った株には害虫もつきやすく、庭全体の健康にも悪影響を及ぼすリスクがあります。
ホワイトセージの代わりにおすすめの庭の植物


「ホワイトセージを庭に植えたかったけど難しそう…」という人は少なくありません。
そんなときは、見た目の美しさや扱いやすさで代わりになる庭木を選ぶのがおすすめです。
ここでは、日本の環境に合いやすく、外構や庭づくりで人気の高い樹木を紹介します。
シマトネリコ|丈夫で管理しやすいシンボルツリー
シマトネリコは常緑樹で、一年を通じて緑を楽しめる庭木です。
成長は早めですが、耐暑性・耐湿性ともに強く、日本の庭でも育てやすいのが特徴
。株立ち状の樹形が自然でおしゃれな雰囲気を演出し、ホワイトセージの代わりに爽やかな印象を庭に与えてくれる樹木です。
オリーブ|洋風ガーデンにぴったり
銀色がかった葉が魅力のオリーブは、ホワイトセージのシルバーリーフを求める人に特におすすめです。
乾燥気味の環境を好み、日本の庭でも比較的育てやすい樹木です。実をつける楽しみもあり、洋風の外構やドライガーデンとの相性は抜群です。
ソヨゴ|成長が穏やかで上品
ソヨゴは成長がゆるやかで、大きくなりすぎない庭木です。常緑でありながら樹形が乱れにくく、手入れが楽なのが大きなメリット。
赤い実をつけることもあり、庭に季節感を与えてくれます。ナチュラルで上品な雰囲気を演出したい人に向いています。
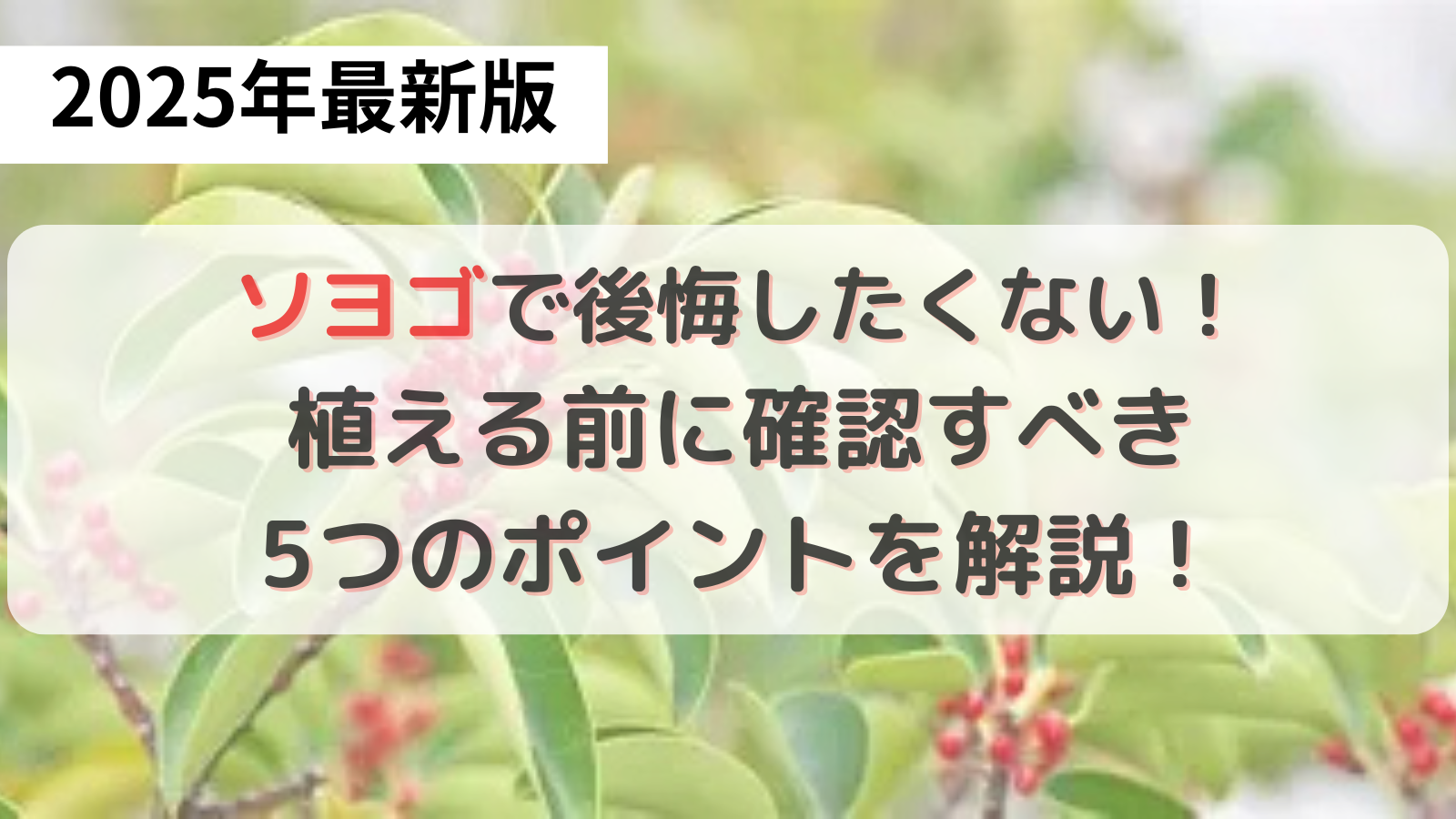
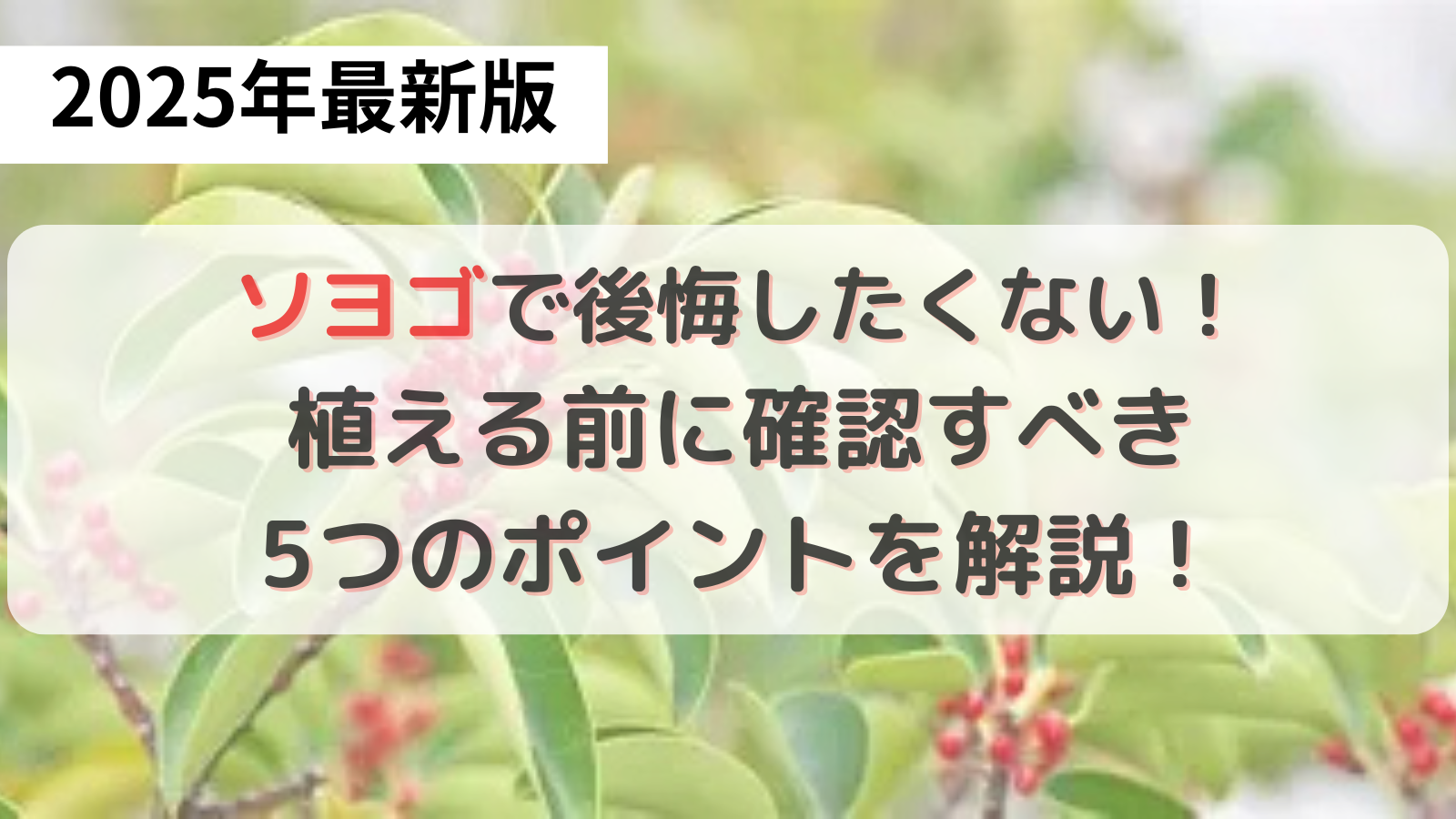
常緑ヤマボウシ|花も楽しめる万能樹
常緑ヤマボウシは、美しい花を咲かせる庭木で、シンボルツリーとしても人気があります。
病害虫に強く、比較的丈夫で扱いやすいのが魅力。
花も楽しめるため、ホワイトセージ以上に「観賞性と実用性を兼ね備えた庭木」としておすすめです。
👉 このように、ホワイトセージのようなシルバーリーフや雰囲気を求めるならオリーブ、庭全体の管理のしやすさを優先するならシマトネリコやソヨゴがおすすめです。
ホワイトセージの風水的な意味
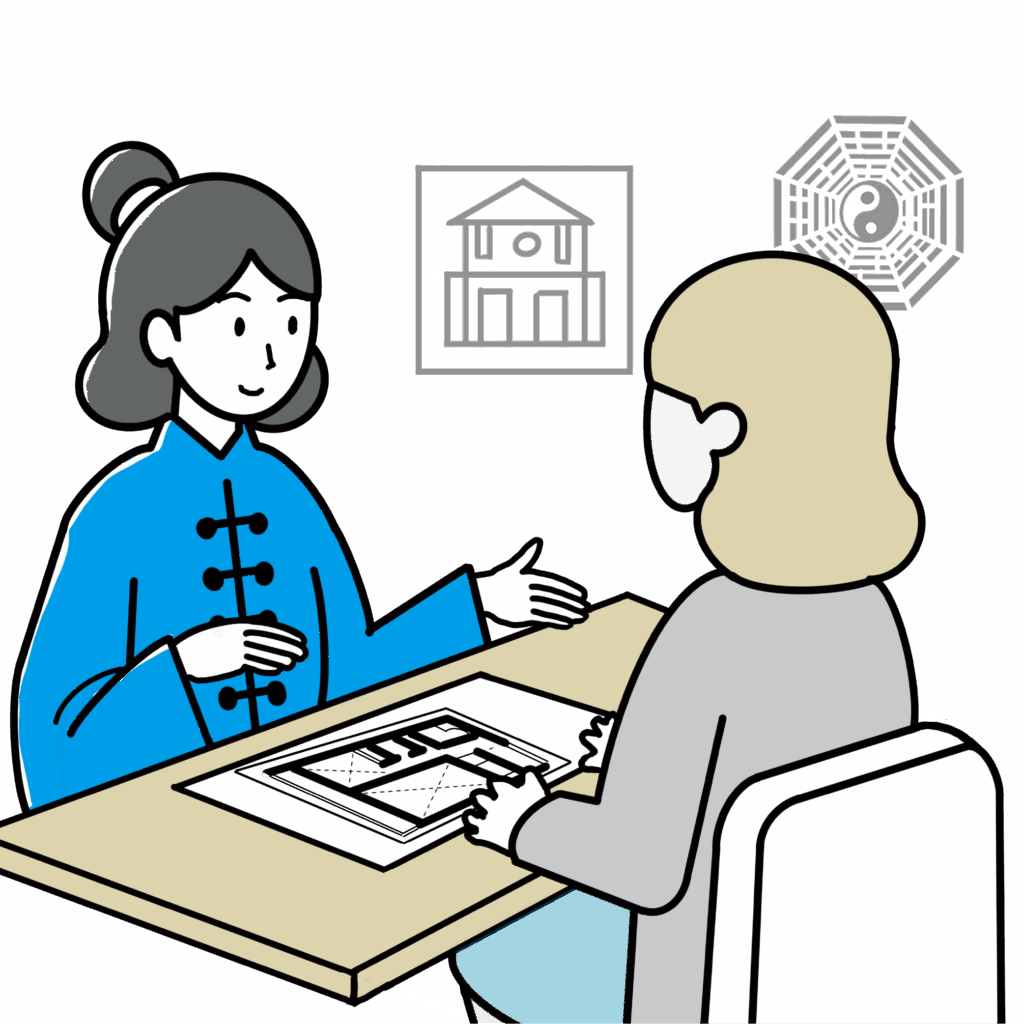
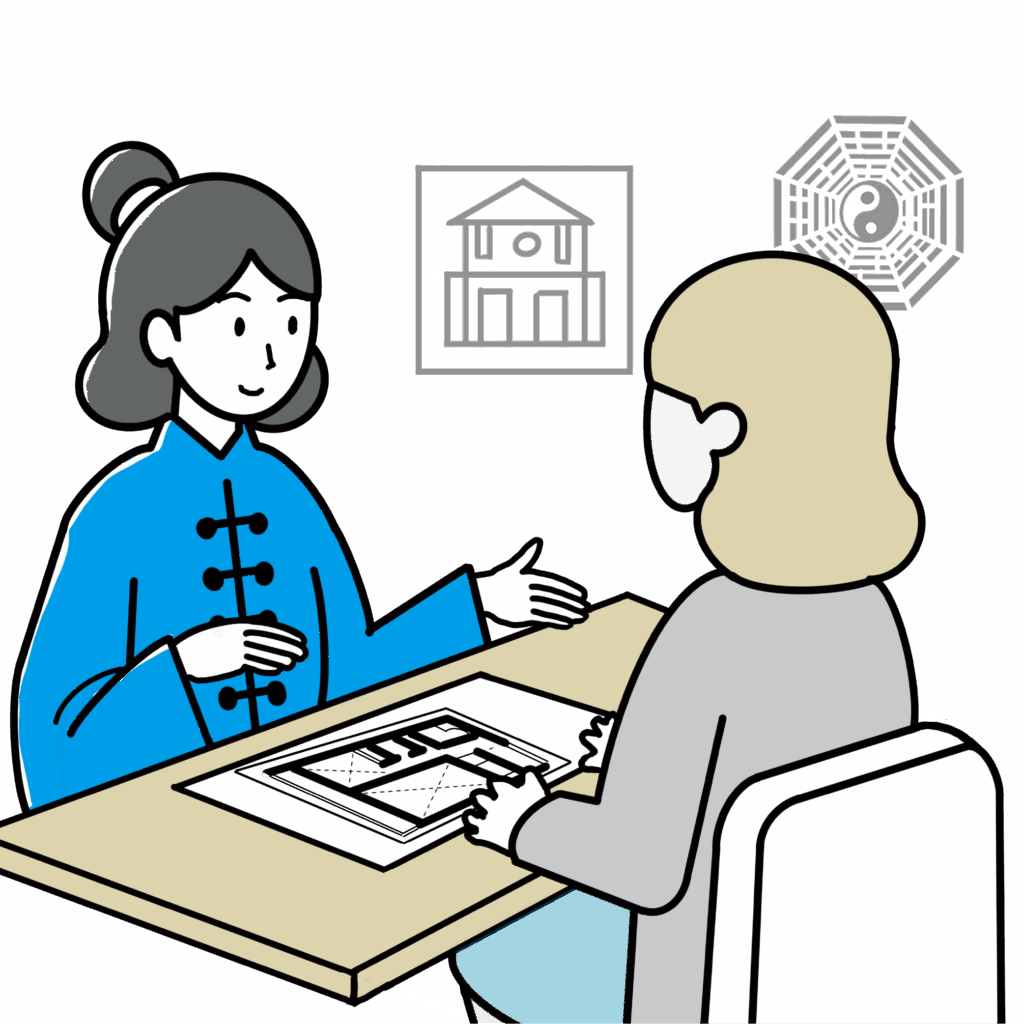
ホワイトセージは古くから「場を清める植物」として知られており、風水やスピリチュアルの世界でも重要な役割を担っています。
ただし、庭に植えるとなると「良い影響」と「注意すべき点」の両面があるため、バランスを理解して取り入れることが大切です。
浄化作用によるポジティブな効果
ホワイトセージは、葉を乾燥させて焚くことで煙が立ち、空間を浄化するといわれています。
風水的にも「邪気を払う」「気の流れを整える」とされ、家にホワイトセージがあるだけで安心感を得られる人も多いです。
そのため、鉢植えで室内や玄関先に置くことで、風水的にプラスの効果を得られると考えられます。
庭に植えるとエネルギーが乱れる可能性
一方で、風水においては「土地や環境に合わない植物」を庭に植えることは運気の乱れにつながるとされます。
ホワイトセージは本来乾燥地帯の植物で、日本の湿気の多い環境には不向きです。
そのため庭に植えると株が弱りやすく、「衰退の気」を呼び込む可能性があるとも言われています。
家との相性を考えることが大切
風水では植物と家の相性も重視されます。ホワイトセージは強い浄化作用を持つため、置き場所を誤ると「必要な縁や運気まで流してしまう」と考える流派もあります。
特に庭に無理に直植えするよりは、鉢植えでコントロールしやすい形で取り入れるほうが、風水的にも安心です。
👉 このようにホワイトセージは風水的に魅力がありますが、庭植えは避け、鉢植えで活用するのが望ましいと言えます。
ホワイトセージとマメ科植物全般との違い


庭木や家庭菜園では「マメ科の植物」は人気があります。クローバーや藤(フジ)、エンドウ豆やソラマメなど、観賞用から食用まで幅広く育てられているのが特徴です。
では、ホワイトセージはそれらマメ科植物とどのように違い、注意すべき点はどこにあるのでしょうか。
マメ科植物は土壌を豊かにする
マメ科植物には「根粒菌」という微生物が共生しており、空気中の窒素を取り込んで土壌を肥沃にする働きがあります。
そのため、他の作物や植物と一緒に育てても相乗効果が得られやすく、家庭菜園や庭に植えても失敗しにくいのが特徴です。
ホワイトセージはシソ科で性質が異なる
一方、ホワイトセージはシソ科アキギリ属の植物です。根に根粒菌を持たず、土壌改良効果もありません。
むしろ乾燥地帯原産で水はけを強く求めるため、日本の一般的な庭土では育ちにくいという違いがあります。
共存のしやすさにも違いがある
マメ科植物は他の植物と共存しやすく、庭全体を調和させる役割を果たします。
しかしホワイトセージはアレロパシー(他の植物の成長を抑える作用)があるとされ、周囲の植物と相性が悪い場合があります
。庭の景観を乱す可能性があるため、マメ科植物のように「庭に植えれば安心」とはいえないのが実情です。
栽培目的の違い
マメ科植物は食用や観賞用、緑肥など実用的な目的で広く使われますが、ホワイトセージは主に「浄化用」「観賞用」といった限定的な用途です。
庭全体を整える植物というよりも、鉢植えでポイント的に楽しむ植物と位置づけたほうが無難です。
ホワイトセージを庭に植えるなら知っておきたい基礎知識
ホワイトセージは基本的に鉢植え管理が推奨されますが、どうしても庭に植えたい場合は「環境に合わせた工夫」が不可欠です。
適切な知識を持たないまま地植えすると、あっという間に枯れてしまったり、他の植物を傷めたりする恐れがあります。
ここでは庭植えを考える場合に知っておきたい基礎的なポイントを整理します。
土壌と日当たりの条件
ホワイトセージは乾燥した土地を好みます。そのため、日本の一般的な黒土や粘土質の庭土では根腐れを起こしやすく不向きです。
水はけの良い砂質土や培養土を混ぜ込んで環境を整えることが必須となります。
また、日光が大好きな植物なので、庭の中でも一日を通して日当たりが確保できる場所に植えることが条件です。
日陰や半日陰では生育が悪く、枯れてしまうリスクが高まります。
水やりと肥料管理の難しさ
庭植えの場合、雨が自然な水やりとなりますが、日本の梅雨や長雨はホワイトセージにとって大敵です。
過湿で根が傷むため、**雨よけ対策や高植え(盛り土の上に植える方法)**などが必要になります。
また、肥料の与えすぎも禁物です。原産地では痩せた土地で育つため、肥料分の多い日本の庭土ではかえって弱ってしまうことがあります。
ほぼ無肥料でも問題なく育つという点を理解しておくことが重要です。
倒木や剪定リスクを抑える工夫
ホワイトセージは木のように見えても幹が柔らかく、成長すると風で倒れやすくなります。
庭植えの場合は支柱を立てて支えたり、剪定で高さを抑える必要があります。
剪定は春から夏にかけて行うのが基本で、切り戻すことで枝数が増え、株が安定しやすくなります。
また、放任すると姿が乱れて観賞価値が下がるため、定期的な手入れを前提にする覚悟が必要です。
👉 このように庭に植えるには「排水性の改善」「日当たり確保」「雨対策」「剪定管理」が必須になります。実際にはかなり手間がかかるため、やはり鉢植えのほうが無難といえるでしょう。
ホワイトセージを庭に植えてしまった場合の管理方法
「ホワイトセージは庭に植えないほうがいい」と分かっていても、すでに植えてしまった場合にはどうすればよいでしょうか。
完全に放置すると枯れたり、他の植物に悪影響を与えたりする可能性があります。
ここでは、庭に植えてしまった場合でもできるだけ長く健やかに育てるための管理方法を紹介します。
剪定で成長を抑える
ホワイトセージは旺盛に成長するため、放任すると姿が乱れて倒れやすくなります。
そこで、春から初夏にかけて剪定を行い、株の高さを抑えることが大切です。
枝先を切り戻すことで株元が安定し、風にも強くなります。また、剪定した枝葉は乾燥させて浄化用に活用できるので一石二鳥です。
根の広がりや湿気対策
ホワイトセージは根が浅く湿気に弱いため、雨の多い時期は特に注意が必要です。
庭植えしている場合は、株元に砂利を敷いて排水性を高めたり、盛り土をして根が水に浸からないように工夫するのがおすすめです。
倒木防止のための支柱立て
成長とともに幹や枝が細長く伸び、不安定になりやすいのがホワイトセージの特徴です。
強風で倒れたり折れたりしないよう、支柱を立てて固定すると安心です。特に梅雨から台風シーズンにかけては必須の対策です。
病害虫対策を怠らない
湿気の多い日本では、ホワイトセージの葉にカビや害虫がつきやすくなります。
風通しをよくするために株元の枯れ葉を取り除き、蒸れを防ぐことが重要です。薬剤を使わずとも、早めに手で取り除くことで被害を最小限にできます。
移植や鉢上げを検討する
「どうしても管理が難しい」と感じたら、鉢植えに移し替える(鉢上げする)のも選択肢です。
庭植えで消耗してしまうより、鉢でしっかり環境を整えたほうが長く楽しめる可能性があります。
👉 このように、庭に植えてしまった場合でも工夫次第である程度は維持できますが、やはり「鉢植えに切り替える」ことが最も現実的な解決策です。
庭づくりで失敗しないために知っておきたいポイント


ホワイトセージをはじめとしたハーブや庭木は、見た目の美しさや香りの良さに惹かれて「とりあえず植えてみよう」と思ってしまいがちです。
しかし、庭づくりは一度決めたら簡単にはやり直せません。
だからこそ、事前にしっかり計画し、長く楽しめる庭を作ることが大切です。
長く楽しめる植物を選ぶ
豆苗のように一年草で終わる植物ではなく、数年にわたり育てられる多年草や庭木を選ぶと、手間やコストを大幅に削減できます。
- 毎年収穫できる 多年草野菜(ニラ、アスパラガスなど)
- 季節ごとに花や実を楽しめる 庭木(常緑ヤマボウシ、ソヨゴなど)
- 香りや虫よけ効果もある ハーブ類
こうした「持続性のある植物」を選ぶことが、庭を美しく保つ秘訣です。
成長後の姿をイメージする
苗の段階では小さくかわいい植物も、数年で大きく育つと庭全体に影響を与えます。特に庭木の場合は高さや枝張り、根の広がりまで考慮することが必要です。
- 5年後、10年後の姿をイメージする
- 隣家や塀との距離を確認する
- 採光や風通しへの影響を考える
「今の見た目」ではなく「未来の姿」を基準に選ぶことが、後悔を防ぐコツです。
外構や家との調和を考える
庭は単体ではなく、外構や建物と一体で見られる空間です。
洋風の家にはオリーブやシマトネリコ、和風の家にはモミジやツバキなど、家のデザインに合った植物を選ぶことで、全体の雰囲気が引き締まります。
また、植える位置を誤ると「思っていたより日陰になってしまった」「建物に枝が当たるようになった」という失敗につながるため、設計段階で配置をシミュレーションしておくことが大切です。
専門家に相談するメリット
庭木や植物選びを自分だけで決めてしまうと、「見た目の好み」や「その場の思いつき」で判断してしまいがちです。プロの外構業者に相談すれば、
- 土壌や日当たりに合った植物の提案
- 成長後を見据えた設計プラン
- メンテナンスの手間を抑える工夫
など、素人では気づきにくいアドバイスをもらえます。
特に 外構工事一括見積サービス を利用すれば、複数の業者から提案を比較できるため、「費用」と「デザイン」の両面で納得できる庭づくりが実現しやすくなります。
✅ このように「長期的に楽しめる植物を選ぶ」「成長後を想定する」「外構全体の調和を考える」「専門家に相談する」の4点を意識すれば、庭づくりの失敗は大幅に減らせます。
ホワイトセージに関するよくある質問


ホワイトセージを庭に植えるか検討している人や、すでに育て始めた人からよく寄せられる質問をまとめました。実際の栽培や管理で迷ったときの参考にしてください。
Q1. ホワイトセージは日本の気候でも育ちますか?
ホワイトセージは乾燥したカリフォルニア原産の植物なので、日本の高温多湿の環境はあまり得意ではありません。
特に梅雨や台風シーズンには根腐れや蒸れで弱ることがあります。庭植えよりも、鉢植えにして風通しと排水性を確保するのがおすすめです。
Q2. ホワイトセージは冬でも枯れないの?
耐寒性はそこまで強くありません。霜や寒風に当たると枯れ込みやすいため、冬は室内に取り込むか、屋外でも寒さ対策をする必要があります。
関東以北では地植えはリスクが高いといえるでしょう。
Q3. 庭に直植えするとどうなりますか?
直植えすると根が湿気に弱く、雨の多い日本では根腐れの原因になりやすいです。
また幹が細長く伸びるため、風で倒れたり折れたりするリスクもあります。そのため、庭で楽しみたい場合も鉢植え管理のほうが安全です。
Q4. どんな土が適していますか?
ホワイトセージは「水はけのよい土」を好みます。一般的な培養土に軽石やパーライトを混ぜて排水性を高めると、根腐れを防ぎやすいです。
庭の土を使う場合は、水はけが悪ければ高畝にして植えるなどの工夫が必要です。
Q5. 香りを長く楽しむにはどうすればいい?
収穫したホワイトセージの葉は、乾燥させることで香りが強まるといわれています。
日陰で風通しのよい場所に吊るしてドライにすれば、スマッジング(浄化用の煙)やポプリとして長く楽しめます。
ホワイトセージを庭に植えてはいけない まとめ


ホワイトセージは浄化やリラックス効果のある魅力的なハーブですが、庭に直植えすると「倒れやすい」「湿気で枯れやすい」「管理が大変」といった理由から、後悔してしまう人も少なくありません。
特に日本の気候や狭い庭環境には適さないことが多いため、庭木や観賞用として選ぶ際には注意が必要です。
一方で、鉢植えで育てればコントロールしやすく、香りやドライハーブとしての利用も楽しめます。
さらに、庭のシンボルツリーが欲しい場合には、オリーブやソヨゴ、常緑ヤマボウシなどの代替樹種を選ぶことで、管理のしやすさと見た目のバランスを両立できます。
後悔しないためにできること
- 成長後の姿や庭との調和をイメージして植える
- 土壌や気候など環境に合うかを確認する
- 外構や庭木選びは専門業者に相談する
- 一括見積サービスを使って複数の提案を比較する
ホワイトセージに限らず、庭づくりは「見た目の好み」だけでなく、将来の管理のしやすさ・環境との相性・全体のデザインバランスを意識することが大切です。
庭木を選ぶときに少し手間をかけて調べ、プロの意見を取り入れることで、失敗や後悔のない理想の庭を実現できます。
👉 最後におすすめしたいのは、外構工事一括見積サービスを利用すること。
複数の業者のプランを比較できるので、自分の庭に最適な方法を見つけやすくなります。後悔のない庭づくりを目指す方は、ぜひ活用してみてください。
庭木の選び方や手入れは思ったより大変なものです。自分だけで判断すると「思った以上に剪定が大変…」「もっと他に合う庭木があったかも」と後悔してしまうことも。
無料の一括見積サイトを使えば、複数の外構業者から提案を受けられるので、「費用感」や「手入れのしやすさ」を比較でき、納得して決められるでしょう。


「タウンライフ外構工事」を利用すると、無料で複数の業者の見積もりが届きます。
しつこい営業もありませんから安心して利用できます。
庭づくりに悩んでいる方はぜひ利用しましょう。
\ 全て無料 で安心!/